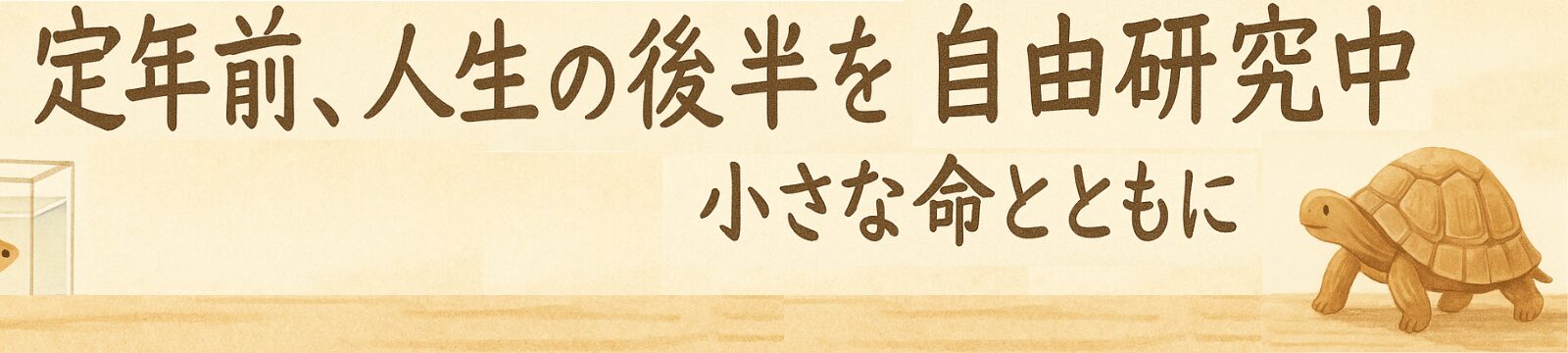2024年9月15日、午後3時57分。秋の風がほんの少し肌寒くなり、午後の日差しが柔らかくなる時間帯。私は三日月院での仕事を終えたばかりだった。その日、何かが足りないと感じていたのは、まかないがないとわかったからだ。昼食も食べずに働いていた自分に、少し呆れながら、次に何をしようかと考えていた。
「よし、まずはお参りだ」
私は神社に行こうと思っていた。三日月院の近くにある富さ神社だ。松のように静かな雰囲気に包まれたその神社は、いつも私を落ち着かせてくれる場所だった。仕事を終えた後の一息つきたいとき、自然と足が向く場所だった。
しかし、その日の予定は急に変わった。神社に向かう前に、三日月院のスタッフが教えてくれた定食屋に立ち寄ろうと考え直したのだ。お腹が空いていたのもあるが、その店のことを聞いたとき、なんとなくその雰囲気が気に入ったのだ。
「ふじふじ屋か。評価は3.7…値段も手頃だし、悪くはなさそうだな」
私はその店の前に立ち止まり、メニューを眺めた。お手頃な価格で提供される蕎麦が評判のようだったが、担々麺の文字が目に留まった。「担々麺、大盛りでお願いします」と注文を決めた瞬間、思わず笑みがこぼれた。これで腹を満たせると考えると、自然と心が軽くなった。
店内は落ち着いた雰囲気で、まるで地元の人々の憩いの場のようだった。壁に貼られたメニューや、古びた木のテーブルが心地よい。そして、そこに座っている人々の会話が耳に飛び込んできた。
「神社行ってからご飯食べるか」と誰かが言う。別のテーブルでは、古い友人たちが集まって近況報告をしているようだった。「あの店、綺麗なママがいるんだよ」などという他愛ない話も聞こえてくる。
「担々麺、お待たせしました」と、店員が大きな丼を持ってきた。湯気が立ち昇り、香辛料の香りが鼻をくすぐる。「これは期待できそうだな」と、私は箸を持つ手を少し高揚させた。
一口目を食べた瞬間、スパイスの効いた辛味が広がり、口の中で何とも言えない幸福感が満ちた。ピリッとした辛さの中にある深い旨味。これはただの担々麺ではなかった。まるでこの一杯が、長い一日の疲れを一気に癒してくれるようだった。
「やっぱり、ここに来てよかったな」
ふと外を見ると、神社への参拝客たちがぞろぞろと歩いている。お祭りの縁日が開かれているようで、賑やかな声が聞こえてくる。私は少し落ち着いた気持ちで、食事を終えると、神社へと足を向けた。
富さ神社の境内に入ると、薄暗くなり始めた空の下、提灯の灯りがぼんやりと照らしていた。人々のざわめきが耳に心地よく響く。お参りを済ませた後、私は縁日の屋台を見て回った。焼きそば、たこ焼き、綿菓子の匂いが混ざり合い、どれもこれも美味しそうだ。
「やっぱり日本の祭りはいいな」と、私はひとりつぶやく。
屋台のひとつに、行列ができているかき氷屋があった。何か特別なトッピングがあるのだろうか、興味をそそられたが、さすがに担々麺でお腹が満たされた後では食べる気にはならなかった。それでも、にぎわう人々を眺めているだけで十分に楽しめた。
「よし、次はあの屋台に行ってみよう」と、気まぐれに歩き出す。ふと、誰かが「ギャグの方行っちゃってる」と笑いながら言う声が聞こえてきた。その声に乗って、私の足は自然と笑顔を浮かべた。
神社を後にして帰り道、私は今日の出来事を振り返った。思わぬ出会いや予定の変更があったが、それもすべてが心地よいリズムを刻んでいた。空腹だったことから始まり、美味しい担々麺を食べ、神社での静かな時間を過ごし、祭りの賑わいを楽しむ――そんな何気ない一日が、私にとっては特別なものになっていた。
「やっぱり、こういう何気ない日常が一番だな」
ふと、また神社に行く機会があれば、その時も同じように定食屋を巡って、何か新しい発見をしてみようと心に決めた。日々の些細な出来事の中に、予期せぬ喜びが詰まっているものだ。今日はまさに、その一日だった。
そして、家に着いた私は、静かな夜の時間を楽しみながら、明日もまた、同じように美味しい食事と穏やかな一日が待っていることを願った。
「感謝だな」と、私は小さく呟き、深い眠りに落ちた。